『オエッ!』とならないよう、気をつける方法ってないの?
という疑問に、約200人の赤ちゃんの食事指導に関わってきた歯科衛生士がお答えします^^
赤ちゃんの離乳食って、
- むせないよう
- 喉につまらせないよう
- 咳き込まないよう
と、なにかと気をつかいますよね。
でも結論から言えば、離乳食でむせてしまう原因は、
- まだ赤ちゃん自身の食べる準備ができてない
- 柔らかい離乳食ばかり食べさせている
かもしれないんです。
とくに生後7ヶ月未満から離乳食を始めている場合は一旦やめ、
おっぱいやミルクを十分与えた方が、じょうずに食べる子になるんですよ^^

この記事を読めば、赤ちゃんがむせる原因と対処法が分かります^^
ぜひ参考にして、安心して赤ちゃんと食事ができる時間をつくりましょう。
6ヶ月頃の赤ちゃんが離乳食でむせる原因

生後6ヶ月未満の赤ちゃんが離乳食でむせる原因は、
まだ赤ちゃん自身の「食べる準備」ができてないからかもしれません。
なぜなら、赤ちゃんの離乳食って
②お座りがしっかりできる(姿勢が安定している)
③手が自由に動く
の3つの条件がそろう、生後7ヶ月目以降のスタートが1つの目安になるからです。
逆に5ヶ月や6ヶ月など早い時期から離乳食を開始している場合は、
3つの条件がそろう生後7ヶ月まで、一旦お休みたほうがいいんですよ^^

詳しく説明します^^
おっぱいやミルクがしっかり飲めない
赤ちゃんはおっぱいやミルクをしっかり飲むことで、
食べ物を『噛む→飲み込む』という『口の動きの基礎』を身につけています。
実は赤ちゃんって、おっぱいを『吸って』飲んでいるんじゃないんです。

この動画の55秒あたりの
『舌・あごの動き』を見てください^^
赤ちゃんって舌で乳首を上あごに押し付け、搾り出すようにおっぱいを飲んでいますよね。
この『舌』の動きを繰り返すことで、離乳食になったとき、
食べ物をスムーズに喉に送ることができるんですよ^^

つぎに、『あごの動き』を見てみましょう。
動画を見ると、おっぱいを飲むたびに、赤ちゃんのあごが『上下』に動いていますよね?^^
この『あご』の動きこそ、『噛む』ときの口の動かし方^^
つまり、しっかり母乳やミルクを飲んだ赤ちゃんは、
自然に食べ物を『噛む→飲み込む』という口の動きができるようになるんです^^

その結果、離乳食が始まっても
スムーズに食べられるようになるんですよ^^

反対に、『吸って飲むタイプの哺乳瓶』を使っていた赤ちゃんは、
十分『口』や『舌』を動かす練習ができていません。
このタイプの哺乳瓶は、乳首の先に穴が開いただけの造り。
口先だけで吸えば、簡単にミルクを流し込めてしまいます。

『あご』や『舌』をつかう練習ができない、哺乳瓶なんです。
その結果、飲み込むのが下手になり、むせやすくなってしまうのです。
\おすすめ哺乳瓶は、こちら!/

お座りがしっかりできない
5〜6ヶ月ってまだ姿勢が安定してないし、お座りさせてもフラフラしてますよね。
姿勢が安定してないと、赤ちゃんは上手に食べられなかったり、むせる原因になります。

想像してみましょう。
あなたが寝たきりになった場合、不安定な姿勢で食事をしたら…むせてしまいますよね。

これは赤ちゃんだって同じ。
だからこそ離乳食の開始は、お座りがしっかりできて姿勢が安定する生後7ヶ月目以降からスタートしてほしいんです^^

もちろん姿勢が不安定なら、もっとあとからスタートしてOK^^
離乳食のスタートって、育児書によっては5カ月や6カ月からとも書かれていますよね。
でも姿勢も問題はもちろん、早すぎる離乳食はアレルギーの原因になる可能性もあるんですよ。
\理由はこちら/

手が自由に動かない
赤ちゃんって、しっかりお座りができるようになると、手も自分の意志で動かせるようになります^^

人間って、手で食べ物を持って口に入れますよね!
つまり『手が自由に動かせる』ことも、離乳食がじょうずに食べられる『サイン』になるんですよ^^
しっかりお座りができ手が自由に動かせるようになると、赤ちゃんの食べる能力はドンドン上がっていきます。
すると、
- ご飯
- 野菜の煮物
など「大人と同じもの」でも、胃腸が慣れると平気で食べられるようになるんです^^

え?歯がなくても!?

そうなんです^^
しっかりおっぱいを飲んだ赤ちゃんは、たとえ歯がなくても、
おっぱいを飲むときのように『舌』を上あごに押し付けて食べようとします。
そして成長すると歯ぐきで食べるようになり、歯が生えてくると、歯で噛んで食べるようになるんですよ^^
\歯がなくても食べられる理由はこちら/


反対に手が自由に動かせないうちは、一生懸命離乳食をつくっても、
じょうずに食べられません…。
だから5ヶ月や6ヶ月など、早い時期に離乳食を始めたり、紹介した3つのサインがまだのときは、
生後7ヶ月以降まで、離乳食はお休みしたほうがいいんですよ^^
離乳食でむせる・咳込まない子にするため知ってほしいこと

離乳食開始は
②お座りがしっかりできる(姿勢が安定している)
③手が自由に動く
3つのサインが整った、生後7ヶ月以降が1つの時期。
しっかりおっぱいを飲んだ7ヶ月以降の赤ちゃんなら、たとえ歯がなくても大抵のものは食べられます^^
姿勢がしっかりしていれば、むせることもほとんどありません^^

赤ちゃんはおっぱいの飲み方を、『本能』で知っています。
でも食べることは『練習や経験』して、あとから身につけていくもの。

練習できないと、むせる原因になってしまうんです。
そもそも食べ物を飲み込むには、
↓
②ほっぺたや舌を使って、歯の上に食べ物をおく
↓
③よく噛んで、唾液と混ぜて飲み込みやすい形にする
↓
④舌を使って喉へ送り込み、飲み込む
という4つのステップが必要です。

そしてこの一連の『口の動き』は、
本来『おっぱいを飲むこと』で鍛えられています^^
おっぱいをしっかり飲んだ子は、離乳食が始まっても(初めは上手に飲み込めないかもしれませんが)、
練習や経験を重ねるうちにじょうずに食べられるようになるし、
『これくらいなら飲み込めるな!』と、自分で分かってきます^^
だからこそ、6ヶ月など早い時期に離乳食を始めているときは、7ヶ月まではしっかりおっぱいを飲ませ、
『噛む→飲み込む』といった口の動きの練習期間に当ててほしいんです。
その方が、7ヶ月になったときスムーズに食べられる子になるし
むせても、次から工夫して食べられる子になってくれますから^^
赤ちゃんが離乳食でむせた時の対処法

繰り返しますが、赤ちゃんが生後7カ月を過ぎ
②お座りがしっかりできる(姿勢が安定している)
③手が自由に動く
なら、食べ物が喉につまることはまずありません。
つまってしまう可能性があるので注意が必要です。
もし、むせたとしても『噛む⇒飲み込む』という口の動かし方は、おっぱいを飲みながら経験しているので、
次からは赤ちゃんなりに慎重に食べるようになるんです^^

むせると、離乳食をあげるのが怖くなりますよね…。
でもむせる経験も、赤ちゃんにとっては必要なこと^^
歩きだす頃も、何度も転んで、頭や手を打ちながらうまくなりますよね。

最初から上手に歩ける子なんていません^^
これは食べることも同じ^^
だからもし赤ちゃんがむせてしまっても、
「大切な経験をしたね」と大きな気持ちで見守って欲しいのです。
それに赤ちゃんが食べるときは、大人が必ず側にいますよね。
万が一むせても
・喉に手を入れて、つまったものをとる
・逆さまにして背中をトントンする
など、冷静に対処してあげれば問題ありません^^

うちの子も8ヶ月のとき、枝豆を喉につまらせた経験があります。
そのときは背中を叩いて出してあげましたが、
その失敗のあとからは1度もつまらせることがなくなったんです^^

彼女なりに、うまく飲み込むコツを掴んだようです^^

赤ちゃんの離乳食は生後7ヶ月から始めよう

赤ちゃんの離乳食は
②お座りがしっかりできる(姿勢が安定している)
③手が自由に動く
の3つの条件がそろう、生後7ヶ月以降から始めましょう。
さらに、離乳食をむせずに食べられる子にするには、
柔らかい離乳食ではなく、口や舌をたくさんつかえるメニューにすることも大切です。
\柔らかい離乳食のデメリットはこちら/

繰り返しますが、お座りができ手が自由に動くようになると赤ちゃんの食べる能力はグングン上がってきます!

歯がなくても、『歯ぐき』や『舌』で食べられるようになります^^
だから基本的に離乳食は、
・煮物の野菜
など、大人の食事の中から食べられそうなものを取り分けていきましょう。
もちろん固形物に胃腸が慣れるまでは、1日1回から始め、
体調が良さそうなら、1日2回・1日3回と、どんどん回数や量を増やしていきましょう^^
赤ちゃんは、口にモノが入るとまず飲み込もうとします。
でも「飲み込めない!」と分かったとき、初めて噛むようになるんです。
反対に柔らかい離乳食では、噛む練習できないため、丸飲みやむせる原因になってしまいます。

『大きいかな?噛めるかな?』と、心配になる気持ちも分かります。
でも、「食べれる・食べれない」は赤ちゃんが決めていくこと!ですよね?^^

あなたの赤ちゃんは賢いです^^
もし大きくて飲み込めないときは、むせるより先に口から出してくれますから。
むせないよう離乳食を柔らかく小さくすることは、赤ちゃんの「食べる練習」するチャンスを、
わたし達大人が奪っているとも言えます…。
だからこそ、生後7ヶ月で離乳食を開始したら、どんどん噛むチャンスをつくってあげてほしいのです^^
▼7ヶ月からの離乳食の進め方は、こちらが参考になるのでぜひ▼

赤ちゃんが離乳食でむせる原因と対処法まとめ
離乳食でむせるのは、時期が早すぎるのかもしれません。
離乳食開始の目安は
②お座りがしっかりできる(姿勢が安定している)
③手が自由に動く
3つのサインが整った、生後7ヶ月以降が1つの目安です。
だから6ヶ月など早い時期に離乳食を始めるより、7ヶ月まではしっかりおっぱいを飲ませ、
『噛む→飲み込む』といった口の動きの練習期間に当ててほしいんです。
その方が、スムーズに食べられる子になるし、
むせても自分で工夫しながら食べられるようになりますから^^
▼7ヶ月からの離乳食の進め方は、こちらが参考になるのでぜひ▼




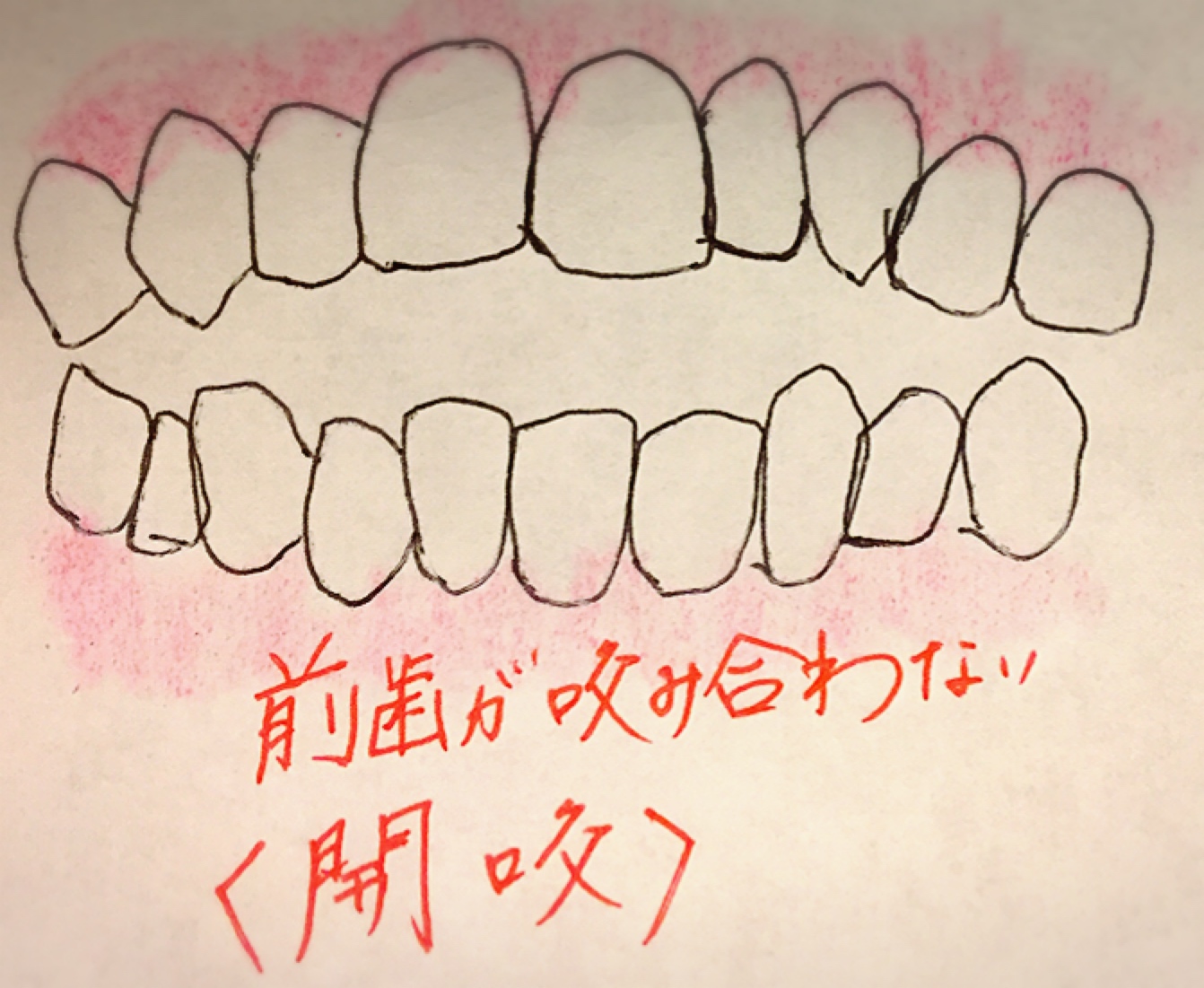
コメント